ここで話を止めることもできる。
学長が昔お気に入りだった候補生に似ているからという理由で、自分にそいつの名前をつけた。だから、自分はその名前で呼ばれるのは嫌いだと。身代わりなんてやってられないと。
学長の寿命が迫っていて、サイマスが最後の希望を求めた。教師たちが急ぎ、セントラルで「特殊前線指揮官」の素質を持つ者がいないか調査したら、自分がそうだった。
だから、慌ただしく、その日のうちに連れて来られた。
士官学校そのものでもあるサイマスが命を終えれば、「正しい判断能力を持つ士官」が新しく生まれないことになる。
そうなれば、この世界を守る軍はどうなっていくか。
それだけじゃない、世界自体が終わりに近づいている……いや、世界が終わりに近付いているから、サイマスも死ぬのか?
どっちにしろ、ろくでもない情報だ。
「……クライン?」
しばらくの間、黙って待っていたリガンドが遠慮気味に自分の名前を呼んでくる。
止めるか、続けるか
「……世界が終わる」
「……え」
こんな突拍子もないこと、聞き返すのは当然だ、だけど、構わずに言葉を続ける。
「その前に、サイマスが終わる。学長はもう、そんなにもたない」
隣からの言葉はない。
「学長はこの士官学校の機能そのものだ。だから、学長が死ねば、士官学校は機能を停止するし、そうなれば、軍に新たな士官が増員されることもなくなる。第一防衛だけで世界を守り続けるのは無理だし、正しい判断を下す士官が減少すれば、第二防衛がどうなるか…」
勢いよく、吐きだした。 こんなことを突然聞かされて、隣にいる自分のバディが、今、どんな表情をしているのかわからない。見るのが怖い。
……怖い?世界が終るとか、軍が崩壊するとか突然聞かされた側の身になれよ。士官学校を卒業して待ってる世界が、終わりしかない、救いのない戦いに満ちていることを知らされる方が、余程怖いだろ…!
自棄になって、自棄になったつもりで、起き上がる。
ずっと伏せていて状況がよくなるっていうのなら、いつまでも待ってるさ。でも、現実はそうじゃない。
起き上がると、リガンドと目が合った。
何かを言いたげな目に、手を、その頬に伸ばしかけて、気力が尽きて腕を降ろす。
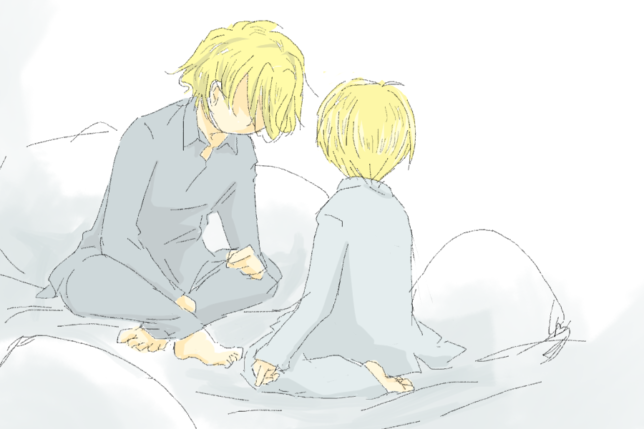
「……ごめん、巻き込んで。知りたくなかっただろ……こんな、世界が終わるとか、最低な話……」
下を向いて瞼を強く閉じ、リガンドの顔を見ないまま話す。
ハインツには「話すなら俺から話す」と言っておいて、裏門のことについては結局丸投げして、世界のことについては『判断』に迷いに迷って、これだ。
傍にいる誰かに自分の不安や不満をぶちまけたいだけ、そんな理由で巻き込んだ。
その上、自分が情けないと自分を責めることもしたくないし、できない。「無理なことは無理だ」と、世界に責任を押し返して、文句を言ってやりたかった。……無理だ。
空気がゆっくりと揺れて、降ろした手に温かな手が重なる。
俯いて閉じていた瞼を開かなくてもわかった。
数秒の、短い重なりに、思わず息を止める。
漏れた息が混ざり合って、瞼を開く。
再び広がる視界の中で、こちらを見上げるリガンドが綺麗にほほ笑んだ。
「あのとき、クラインが俺を拾ってくれてなかったら……俺の世界は終わってたから 」